口コミに 耳を澄まし、検証する SNS時代にリテラシーを/西山 守 准教授
世界の秘境や社会問題をドキュメンタリーとして映し出してきた田淵俊彦教授。教育現場でこそ伝えたい、映像制作の本質と、表現活動を通して学生に育んでもらいたい力について、思いを明かしました(聞き手:桜美林大学 畑山浩昭学長)。
ドキュメンタリーに活路を見出し
世界の「違い」を映し出す
畑山:田淵先生はテレビ東京に長くお勤めでした。就職先を決める時には、はじめからメディア系に絞ったのですか。
田淵:いえ、法学部の学生だった私は当初、「弁護士になろうかな」などと考え、刑法のゼミに入りました。そこで少年法を学ぶ中で、テレビドラマが少年犯罪に及ぼす影響について研究してみようと思い立ちました。たまたまゼミの先輩で東京の民放キー局に勤務する人がいて、テレビの世界のことをいろいろ話してくれて、「面白そうだな!」と。それで入社を決めました。
畑山:それは面白い志望動機ですね。テレビ東京では、ドキュメンタリー番組の制作に携わったそうですね。
田淵:最初は歌番組などを担当しました。80年代のアイドルが活躍していた頃です。そこから経験を積んでディレクターになりかけの入社4、5年目の時に任されたのが、チベットを紹介する番組の制作。現地でいろんな経験をして感銘を受け、ドキュメンタリーに初めて興味が湧きました。その後、私は子会社の制作会社に出向を命じられることに。今でこそ頻繁にある異動ですが、まだ若いうちから関連会社に出向を命じられるのは当時としては珍しく、左遷されたと思い込みました。「この先、自分でどういう道を切り拓くか」と考えた時に思い出したのが、チベットに行った経験でした。会社の中を見回すと、ドキュメンタリー番組を手がける人が他にいなかった。「誰もやってないなら、やってみよう」。そう心に決めました。

畑山:歌番組の担当から、ガラッと雰囲気が変わりましたね。
田淵:秘境に行って、少数民族の人たちと出会って、目から鱗のことばかりでした。これまでの自分の常識を取り払う、いわゆる「アンラーン(unlearn)」のような体験をしました。例えば現地の人に「あなたは今、幸せですか?」と質問すると、彼らには質問自体の意味がわからないんですよ。「幸せですかなんて聞かれたことがない」って。私の生きてきた世界とまったく異なる世界に触れることの快感を覚え、「どう違うか」を描き出すことに取り組みました。
畑山:これまで世界のさまざまな場所を訪れたそうですね。
田淵:100カ国を超えていると思います。辺境の地ばかりで、一度旅に出ると一気に数カ国回りました。社内ではそんなフィールド系のドキュメンタリストはいなくて、他局の先輩を探し、いろいろアドバイスを聞いて回りました。そして昔の本や、民俗学の専門書を読みあさり、カメラが入っていない場所を見つけては「ここに行ってやろう」と。そんな感じで、動いていました。


次世代につなぐ
映像を通じた社会への問いかけ
畑山:お話を伺っていると、文化人類学者のようですよね。いっぽう、ドラマ制作にも携わった頃があったのですよね。
田淵:よく、「ドラマとドキュメンタリーって、まったく違いますよね」と言われるんですけど、そうでもなくて。例えば貧困問題をドキュメンタリーで描こうとすると、事実を描くしかないので、暗い話になってしまう。けれども、ドラマで描くのであれば、暗い部分だけではなく、フィクションによって何か明るいものを描き出して補えることもあります。私としては、描き方が違うだけで「同じだな」と思います。物事を見る時に、片面しか見えていないけれど、そこに必ずある裏面を想像してみることが大切です。それは、私がドキュメンタリーとドラマの両方取り組んだから気づけたことだと思います。
畑山:それぞれの現場では、どのような役割を担っていたのですか。
田淵:ドキュメンタリーではディレクターとプロデューサーの両方やっていたんです。自分で企画を立てて、金額の交渉もする。ドラマではプロデューサーの仕事に専念しました。ドキュメンタリーはスタッフが少人数ですから、自分がディレクターとして撮りに行けばいい。それに対してドラマは大がかりで多くのスタッフが関わるので、監督の力を借りつつ、自分はプロデュースを実行していく。こういう考え方でやってきました。


畑山:テレビ局から、大学に移られたきっかけは。
田淵:ここ最近、テレビ業界では若い人たちを育てるという気風が薄れてきたと感じるようになりました。マネタイズばかり声高に叫ばれるようになってしまった。桜美林大学をはじめ、いくつかの大学で非常勤講師を10年ほど勤めるうち、「映像でカタチにして表現し、人々に伝えていく」というマインドを、私ならば次世代に継承できるんじゃないかと感じるようになりました。そんな使命感が生まれたんです。
畑山:私にも共通する思いがあります。私たちの学生時代は、本当に自由で、好きなことを勉強し、好きなことをやってきました。今、全国の多くの大学が学生募集に苦労する中、生き残りをかけた競争に尽力するあまり、「本来、大学ってこんなに自由なところだよ」ということを、学生に十分に伝え切れていない気がします。本質をいま一度語り合って、それをカタチにすることが大切だと思っているんです。
田淵:近江商人の経営理念の言葉で「三方よし」という言葉がありますよね。「売り手よし、買い手よし、世間よし」。その一つの「世間よし」が薄れてしまったように感じます。映像の世界は元来、良い作品をつくり、誰かを感動させ、それで自分たちも生計を立てられて、そしてその先に「放送文化で社会を豊かにする」という思いがあったはずです。まさに、桜美林大学が掲げる「学而事人」ですよね。映像を使って社会のためになり、社会に何かを訴えかける。実は一番大切なことが、最近はないがしろになっている。映像に限らず、社会全体の潮流にも通底すると思います。 私が学生たちにいつも語りかけているのが、「なぜ映像を学ぶのかを考えてほしい」ということ。誰かを感動させて嬉しい、それでお金を儲けられればまた嬉しい。でも、さらに「社会にどういう影響を与えられるのか」を考えてほしい。それが肝だと考えています。
データ化できない
表現や自己肯定感を育む
畑山:今、社会は数字を崇拝し、データ主義にとらわれ過ぎで、人文社会系の「創作や創造的なもの」が横に置いてしまわれがちです。本学の芸術文化学群の学生たちは、自分の感性をカタチにする「表現者」になるための専門教育を受けます。何かを「伝える」ということは、オーディエンスに対し、どう提示すれば最も伝わりやすいのか、そこに心血を注ぐことに尽きます。演劇・ダンス、音楽、ビジュアル・アーツも、データ主義では到底収まらない分野で、今後、改めて脚光を浴びていくはずです。
田淵:おっしゃる通りです。私のゼミでは、就職活動の一環として、学生たちにさまざまな業界で現場研修を体験してもらいます。芸能事務所でデスク業務を担当したり、編集所で動画制作の研修を受けたり。ドラマの現場で俳優やスタッフたちへ弁当を配る仕事も経験します。一見簡単な仕事に思われますが、弁当を配ることで、どういう役割の人が何人いるか、どういうしくみで現場が成り立っているのかがわかるのです。現場での経験を積むと、学生は大きく変わります。自信を持って、「私はこういう分野・仕事に向いているかも」というのを必ず見つけてきてくれる。
そしてゼミの個々の研究では、論文の代わりに映像を制作してもらいます。例えば、「日韓のドラマの違い」をテーマにする学生もいれば、バラエティー番組のオープニングを局別・時間帯別に比較する学生もいて、どれも視点が面白いです。アイディアを募ると、良い案が次々と出てきます。
畑山:田淵先生ご自身が、今後取り組みたい研究は。
田淵:今ちょうど取り組んでいるのは、長崎・五島列島の奈留島で行われていた「かくれキリシタンの洗礼儀式」の再現映像の制作です。五島列島は「かくれキリシタン」の多かったところです。この地に残る「お授け/別名:角欠き(つのかき)」という洗礼儀式を51年ぶりに再現するプロジェクトがあり、2023年8月に映像として記録しました。今後も研究を続けて、「かくれキリシタン」にまつわる映像をアーカイブ化していきたいと考えています。
畑山:私は鹿児島の出身ですが、九州の西側って面白いですよね。西洋文化と東洋文化が混じったような、独特なカルチャーがあります。それでは最後に、先生が大学での教育について感じていることをお聞かせください。
田淵:メディアリテラシー教育は、社会に出てからでは遅いと思います。学生時代にモラトリアムの時を謳歌してもらいつつ、同時に、社会人に必要な教養・知識を学び取ってほしい。そして、映像教育ではコミュニケーションが大切です。仲間と共に何かを作り出す中で、自分自身を発見できます。学生たちには、数値やデータでは測れない自己肯定感などの非認知能力を高め、自分を見つめ直す機会にしてほしいと思います。

※この取材は2023年9月に行われたものです。
関連記事
-
 百家結集
百家結集 -

「まったくの他者」の物語を通じて自分や社会を見つめ直す/鐘下辰男 教授
百家結集 -

データを駆使し 地域活性化や 学生の学びをサポート/川﨑 昌准教授
百家結集 -

地域との共生を通して 「どう生きていくか」を 考え、語れる人に/石渡尊子教授
百家結集 -

地域や企業と協働し ビジネスの 理論と実践を往復/五十嵐元一教授
百家結集 -

「学びのビュッフェ」と 「探究」の精神で 現代社会の課題に挑む/種市康太郎教授
百家結集 -

多言語教育と「違い」を認め合う学びで コミュニケーション力を磨く/李 恩民教授
百家結集 -

人の心身から航空まで あらゆる分野に気象の視点を/藤田友香助教
百家結集 -

「タッチ」で深める 心と身体の安らぎと社会の温もり/山口 創教授
百家結集 -

「安全」で信頼をつくる空の世界のプロフェッショナル/神戸清行教授
百家結集 -

イラストで橋渡しする科学と社会の間のコミュニケーション/有賀雅奈助教
百家結集 -
.webp)
教育にもデータを リアルとバーチャルを横断する新時代の学びへ/山口有次教授
百家結集 -
.webp)
芸術の価値を育み個人を超えた社会の力へ/能祖將夫学群長
百家結集 -

健康も福祉も縦横無尽の学び 地域社会との共生を実現/河合美子学群長
百家結集 -

広がる空の世界の可能性。ニーズに対応したプロフェッショナルを養成/石川秀和教授
百家結集 -
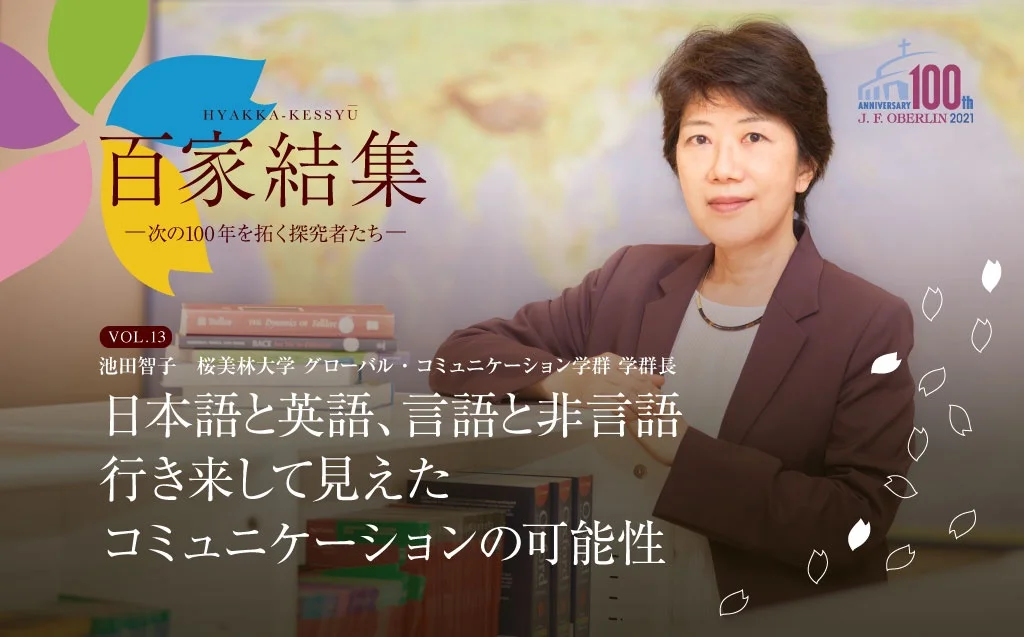
日本語と英語、言語と非言語 行き来して見えたコミュニケーションの可能性/池田智子教授
百家結集 -

あらゆる問題が「見えるようになる」ために いま求められるリベラルアーツの学び/阿部温子教授
百家結集 -
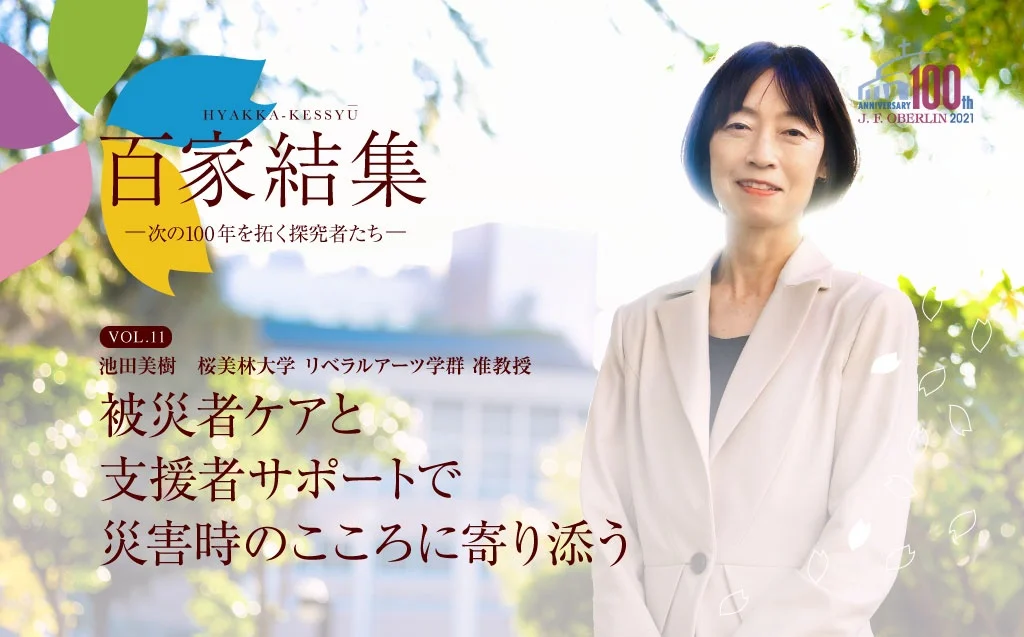
被災者ケアと 支援者サポートで 災害時のこころに寄り添う/池田美樹准教授
百家結集 -

高等教育を底上げし社会に貢献する大学経営の力を/大槻達也教授
百家結集 -

丁寧に、柔軟に、イノベーションを巻き起こす/鈴木勝博教授
百家結集 -

分野を横断して育むオペラの心と音楽人の教養/小林玲子教授
百家結集 -

環境問題を「自分ごと」としてとらえ、解決できる人材を育てる/藤倉まなみ教授
百家結集 -

選手、経営者、研究者 すべての経験を生かしスポーツ振興と教育に尽力/小林 至教授
百家結集 -

問題意識を掘り下げドキュメンタリーで提示 情報社会の知性を問う/大墻 敦教授
百家結集 -

デジタル時代のメディアリテラシーと挑戦の精神を喚起/平 和博教授
百家結集 -

観光立国と超高齢社会へ向けた交通システムを展望/戸崎 肇教授
百家結集 -

高等教育の明日を提言 格差是正と「学修者本位」教育による改革を/小林雅之教授
百家結集 -

大学も“サブスクリプション” 桜美林ならではの価値を伝えたい/畑山浩昭学長
百家結集
ページの先頭へ



