口コミに 耳を澄まし、検証する SNS時代にリテラシーを/西山 守 准教授
難しいと思われがちな科学の話題を、いかに分かりやすく伝え、社会へ及ぼす影響まで考えてもらうか。有賀雅奈助教はそんな課題に、科学の知識とイラスト、社会科学的なアプロ—チも駆使しながら取り組んできました。学生たちには文理の専攻を問わず、科学と社会の間のコミュニケーションを学ぶことで、多面的に思考する力を養ってほしいと語ります(聞き手:桜美林大学 畑山浩昭学長)。
「社会と共にある研究」を意識し
新しい科学コミュニケーションをめざす
畑山:有賀先生は、「研究者」と「デザイナー」というダブルキャリアでご活躍中です。教科書や図鑑、論文などに描かれている、細胞や研究概念図などの「科学イラスト」をご専門としておられますね。そもそも、どうして、この世界に?
有賀:もともとは鳥が好きで、小学生の頃から鳥の研究者になりたいと思っていました。自宅の庭に来るシジュウカラなどを見ては、精巧にできた羽や、身体を観察し、「こんなに小さくても命があるのは、なぜ?」と考えていたものです。鳥の鳴き声を収録したCDを聞き込み、鳴き声を聞けばどの鳥か、分かるまでになっていました。高校生の時には、鳥類研究者たちが集まる学会に顔を出したり、鳥類学を研究する大学の研究室を訪ねたり。次第に「鳥だけでなく、もっと広く生命科学について研究したい」と思うに至りました。
畑山:それは素晴らしいですね。学究肌のご家庭に育ったのでしょうか。
有賀:父は理系で、東北大学の博士課程を中退し、高校教員として勤めていました。それから、じつは母は桜美林大学出身なんです! 中国文学専攻でした。母は私たち子供が生まれてからも中国に留学するなど、生涯かけて中国語を学び続けています。もともと勉学への関心が高い家庭で育ったのだと思います。
畑山:なんとそうでしたか! そういったご家庭の環境もあって、今のキャリアが築かれていったのですね。
有賀:立教大学理学部の時代に、生命科学の先生から「授業を手伝ってほしい」と頼まれたことが、きっかけです。科学の講義の資料をつくる際、「講義内容が学生に伝わらず、間違った理解をされてしまう」と悩んでおられました。「なぜ伝わらず、理解のギャップが生じるのか」と疑問を持った私は、科学と社会の間における情報伝達や対話を促す「科学コミュニケーション」や、その方法のひとつとしての科学イラストの存在を知り、重要性を認識しました。
そこで、修士で進んだ京都大学大学院生命科学研究科では科学コミュニケーションを専門とする研究室に所属し、科学イラストを社会科学的な方法で研究するようになりました。2005年が「科学コミュニケーション元年」と呼ばれ、世間の注目を浴び始めた時期ですが、ちょうど直後にこの世界に入ったことになります。その後、さらに社会学的な手法を学ぶため、北陸先端科学技術大学院大学の博士課程に進みました。
博士号を取得し、東北大学の研究員になると、私が科学イラストの専門家であることを聞きつけた副学長から「大学のさまざまな研究プロジェクトを、一般の方々に説明するスライドをデザインしてほしい」という依頼を受けました。研究者が考えたアイデアをもとに、その研究内容と社会に及ぼす影響を、文章やイラストに表現していく仕事です。私は研究員からデザイナーに転向し、東北大学の研究支援職として多様な研究分野のデザイン制作を担当するようになりました。そのなかで、「社会と共にある研究とは何か」を追究し、その視点を図やスライドに組み込んでいく、新しい「科学コミュニケーション」のスタイルを見出すようになりました。

伝えたいメッセージを見極め
相手の疑問に寄り添うことが重要
畑山:科学のことが分からない人にも、分かるカタチにしていくのですね。よく「分かりやすい言葉に換えて話をしましょう」などと言われますが、もともとの本質的な理解を損なうのでは、という懸念も生じます。先生はどう乗り越えてきたのですか。
有賀:研究者たちは「分かりやすく説明しよう」と思うと、詳細まで説明してしまう傾向があるんですね。それでは情報量がどんどん増えてしまいます。まずは、本当に研究者が伝えたいメッセージを「見抜く」こと、そして余分な情報を「間引く」ことが重要な作業だと思います。そして必用に応じて、平易な言葉への言い換えも試みます。テーマ自体が難しい場合は、関心を引くための表現や見た目の部分も頑張らなきゃいけない。そういったものを組み合わせ、解きほぐしていくイメージです。東北大学のプロジェクトでは、アドバイザーの先生方が、私がつくった資料を見て初めて、研究計画を考えた先生が「何をしたいか」を明確に理解したケースもありました。事前に研究計画について議論をしていたにもかかわらず、うまく伝わっていないことがあったのです。
畑山:「科学コミュニケーション」のなかで先生は、図解にしていくスキルをどう勉強されたのですか。
有賀:デザイン面に関しては基本的に独学です。いっぽう、科学のイラストならではの性質や役割の理解も必要です。私は「科学論」や「科学コミュニケーション」を学んだ経験が重要だったと思います。こうした分野は、科学という営みの特徴や、なぜ社会と科学の間でコミュニケーション不全が起きるのかを理解するヒントをくれるからです。例えば科学の図解の世界って、分野によって「どういうスタイルで描くか」「どういう表現をしたいか」「どこを描きたいか」が異なるんですね。私は科学論という分野でそのような科学の視覚文化を研究しています。
また、「科学は分かりにくい」とよく言われますが、そもそも背景には「市民が知りたいことに科学者が答えていない」という問題や「市民が政府・企業に対し不信感を持っているために、届かない」というケースもあります。例えば、原発やワクチンの問題などは、ただ単に分かりやすく伝えれば納得してもらえるというものではありません。市民の懸念を聞き、応えていく必要がある。市民の気持ちにも寄り添うことが、科学者には求められています。
このため、特に研究内容を市民に伝えるイラスト制作に関わる時には「こういうことも言った方が良いと思います」「この研究の意義を最後に書きましょう」などと科学者に提案しています。それは、ほかの一般的なデザイナーとは違う視点だと思います。
畑山:ジャーナリスティックな側面が多分にありますね。ことにワクチンに関しては、私たち市民はここ数年、さまざまな情報に取り囲まれています……。
有賀:そもそもワクチンを拒否する人たちには強い不信感がベースにある場合がありますので、難しいコミュニケーションになりますが、まずは、根底にある不安に耳を傾け受け止めたうえで、現在どのような情報が社会に広まっているのか、そのなかで誤った情報はどのような経緯で生まれ、どう共有されていったのか、そういうところから市民と一緒に考えていく必要があります。現代では、ワクチンも、AIも、環境問題も……社会で起きていることの多くは科学技術と深く関わっています。「科学コミュニケーション」という分野は、文系・理系という枠を超えた性質を持っていると思います。

科学とのつながりを実感し
多面的に思考する力を養う
畑山:私たちが、私たちなりに人生を送っていくうえで、適切なチョイスをしていきたい。その時に、「科学コミュニケーション」を通じれば情報を理解しやすくなり、正しい判断をしていけるようになる。とても大事なことですね。ところでAIと言えば、最近話題の人工知能ツール「ChatGPT」を、先生はどう見ていますか。
有賀:ちょうど講義でも触れたのですが、新しい科学技術の出現に学生たちは多大な期待を持っています。ところが、彼らに実際に使ってもらうと、「いろいろ問題がある」ということにすぐに気づくんですね。嘘や間違い、偏見のような情報が文章に交ざっていたり、自分が意図していない回答が出てきたり。「ツール」として利用するぶんにはまだしも、「答え」にしてはいけない。それを、身をもって知ってくれました。
このような新しい科学技術は、「科学とは無縁」と思い込んでいた自分たちに深く関わっていることを実感する好機になると思います。私の講義を履修する学生からは「そもそも科学が苦手」という声が多いのですが、授業後には「興味がわいてきた」「苦手だけど挑戦し、視野を広げてみたい」など、意欲的な反応が増えています。そこからさらに専門的な「科学コミュニケーション」のプログラムに、どうすれば参加してもらえるか、いま試行錯誤中です。
畑山:グラフィックデザインが得意な学生は、先生の研究テーマに強く共感するかもしれません。
有賀:リベラルアーツ学群の科目として科学のビジュアル・デザインを学ぶ講義は、2023年秋の3年生科目で初めて開講します。科学に関心のある学生だけでなく、絵やデザインに関心のある学生にも門を叩いてほしいと思っています。大切にしてほしいのは、「見る側の視点を意識すること」。相手が求めている情報とは何か、どう表現したら心に響くのか考えることが重要です。
畑山:そのためには論理的思考が大事ですね。
有賀:おっしゃる通りです。しっかりロジックを持って納得感をもたらすデザインを心がけることが肝要です。「科学コミュニケーション」を通じ、社会・倫理問題、「ChatGPT」の教育上の問題など、じつは身近に科学技術がたくさんあって、自分たちと関わりあっているという実感を持ってもらえたらと思います。そんな視野を身につけて、学生たちと桜美林のリベラルアーツ学群らしい「科学コミュニケーション」をつくっていきたい。多面的思考を鍛え、社会に羽ばたいてほしいと思います。

※この取材は2023年6月に行われたものです。
関連記事
-
 百家結集
百家結集 -

「まったくの他者」の物語を通じて自分や社会を見つめ直す/鐘下辰男 教授
百家結集 -

データを駆使し 地域活性化や 学生の学びをサポート/川﨑 昌准教授
百家結集 -

地域との共生を通して 「どう生きていくか」を 考え、語れる人に/石渡尊子教授
百家結集 -

地域や企業と協働し ビジネスの 理論と実践を往復/五十嵐元一教授
百家結集 -

「学びのビュッフェ」と 「探究」の精神で 現代社会の課題に挑む/種市康太郎教授
百家結集 -

多言語教育と「違い」を認め合う学びで コミュニケーション力を磨く/李 恩民教授
百家結集 -

人の心身から航空まで あらゆる分野に気象の視点を/藤田友香助教
百家結集 -

「タッチ」で深める 心と身体の安らぎと社会の温もり/山口 創教授
百家結集 -

社会に何を問いかけるか?目指すは「三方よし」の映像づくり/田淵俊彦教授
百家結集 -

「安全」で信頼をつくる空の世界のプロフェッショナル/神戸清行教授
百家結集 -
.webp)
教育にもデータを リアルとバーチャルを横断する新時代の学びへ/山口有次教授
百家結集 -
.webp)
芸術の価値を育み個人を超えた社会の力へ/能祖將夫学群長
百家結集 -

健康も福祉も縦横無尽の学び 地域社会との共生を実現/河合美子学群長
百家結集 -

広がる空の世界の可能性。ニーズに対応したプロフェッショナルを養成/石川秀和教授
百家結集 -
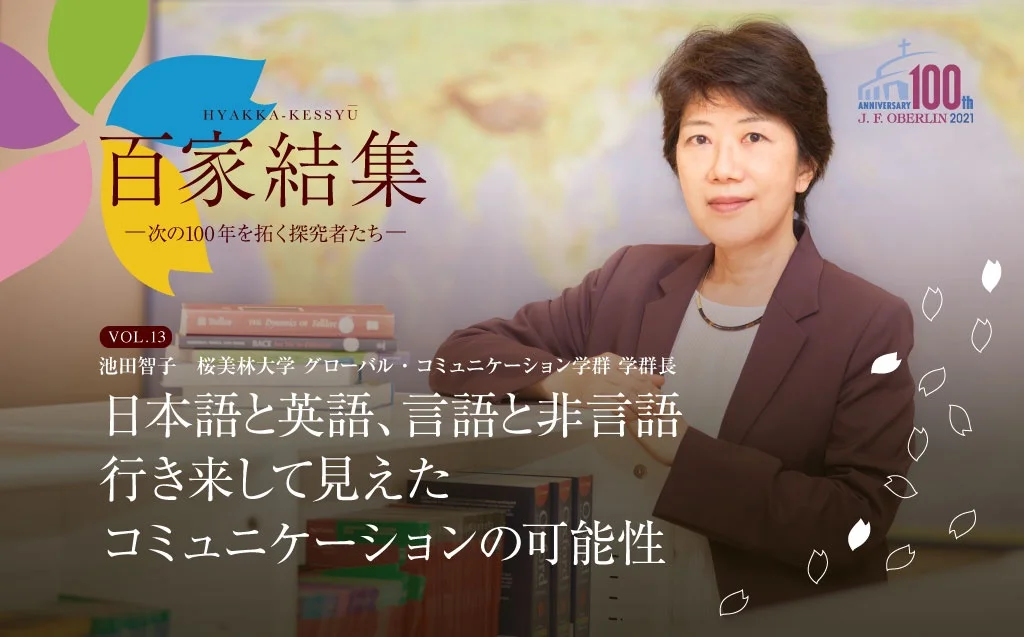
日本語と英語、言語と非言語 行き来して見えたコミュニケーションの可能性/池田智子教授
百家結集 -

あらゆる問題が「見えるようになる」ために いま求められるリベラルアーツの学び/阿部温子教授
百家結集 -
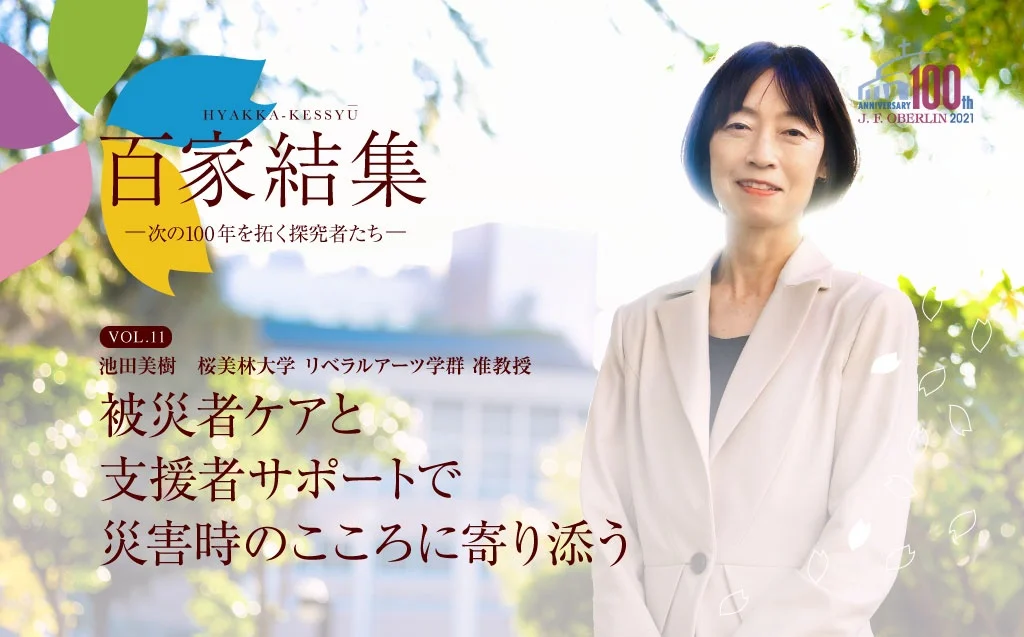
被災者ケアと 支援者サポートで 災害時のこころに寄り添う/池田美樹准教授
百家結集 -

高等教育を底上げし社会に貢献する大学経営の力を/大槻達也教授
百家結集 -

丁寧に、柔軟に、イノベーションを巻き起こす/鈴木勝博教授
百家結集 -

分野を横断して育むオペラの心と音楽人の教養/小林玲子教授
百家結集 -

環境問題を「自分ごと」としてとらえ、解決できる人材を育てる/藤倉まなみ教授
百家結集 -

選手、経営者、研究者 すべての経験を生かしスポーツ振興と教育に尽力/小林 至教授
百家結集 -

問題意識を掘り下げドキュメンタリーで提示 情報社会の知性を問う/大墻 敦教授
百家結集 -

デジタル時代のメディアリテラシーと挑戦の精神を喚起/平 和博教授
百家結集 -

観光立国と超高齢社会へ向けた交通システムを展望/戸崎 肇教授
百家結集 -

高等教育の明日を提言 格差是正と「学修者本位」教育による改革を/小林雅之教授
百家結集 -

大学も“サブスクリプション” 桜美林ならではの価値を伝えたい/畑山浩昭学長
百家結集
ページの先頭へ



