メインコンテンツ
自主的な課外活動で舞台照明の技術を習得
市民ホールでの照明アルバイトで
技術を培った高校時代
舞台照明の仕事と聞いてまず思い浮かべるのは「ステージ上に光を当てること」だろう。しかし、光を当てるとひと言で言っても、光を当てる方向や強弱、色といったさまざまな要素を考慮しなければならない。照明は、舞台というアートワークを完成させるために不可欠なピースなのだ。
こうした「照明デザイン」をテーマにした授業を担当しているのが、芸術文化学群の芦辺靖特任講師だ。桜美林大学で学生の指導にあたりながら、現在も絵本作家ヨシタケシンスケ氏の人気作「りんごかもしれない」や、故・谷川俊太郎氏の詩と絵と音楽をコラボレーションさせた「夏の散歩道」など、第一線の舞台現場で活躍し続けている。
舞台照明に携わるようになったきっかけは、高校入学時に演劇部で活動を始めたこと。演劇自体は物心ついたときから身近な存在だったという。芦辺特任講師が生まれた1970年は第2次ベビーブームが始まる時期で、子どもたちに生の演劇を見せたいという想いから立ち上げられた「子ども劇場」が全国各地で盛んに行われていた。母に連れられて兄や姉とともに月に1回開催される演劇やミュージカル、サーカスなどの公演を観に行く“おでかけ”が何より楽しみだった。その後、兄と姉はともに高校進学後に演劇部に入部。その背中を見ていた芦辺特任講師が、演劇部に入部したのは自然な流れだった。
高校の演劇部では、演者と照明や音響などのスタッフの担当は公演ごとに担当が変わることが多く、芦辺特任講師も照明を含めて一通りの担当を経験した。年3回の公演に向けて制作する部活動から得るものも多かったが、のちに転機となる大きな経験はいずれも学校の演劇部の“外”にあった。
1つは、高校2年生のときに始めた市民ホールでの照明のアルバイトだ。部活動の一環で公演を行う際、照明を担当していた芦辺特任講師は外部から応援に来ていた舞台照明会社のスタッフに目をかけられ、授業がない土日にクラシックやブラスバンドの照明を担当することになった。
「クラシックやブラスバンドの照明では、舞台全体の明度を上げることが主な仕事になります。演奏音を響かせる『音響反射板』と呼ばれる装置を設置して、天井や背景に色を付ければ仕込みは終了です。今なら15分で終わる工程ですが、高校生だった当時は非常に勉強になりました」
また、各校から演劇部員が数人参加して集う町内のリーダー研修も、当時の芦辺特任講師にとっては大いに刺激となった。
「それぞれ異なるバックグラウンドを持った者同士が『演劇』というテーマのもとに集まり、明け方まで語り合った2泊3日は非常に刺激的でした。研修に参加したメンバーで劇団を立ち上げて公演したり、その活動の一環で社会人の方が主宰する劇団ともつながったりと、交流の輪がどんどん広がっていったのです」
こうした経験を経て「演劇の世界で生きていきたい」という想いを募らせ、演劇に関する講義を受けられる大学を複数受験。大阪芸術大学の俳優コースにも合格したが、照明の道に進む選択肢も残しておきたいという考えから、新設されたばかりの近畿大学文芸学部芸術学科 演劇・芸能専攻への進学を決めた。
現役大学生でありながら
公演での照明の現場チーフに抜擢
演技から照明までを幅広く学べる大学への入学を果たした芦辺特任講師だったが、学内公演を行うために用意された劇場には機材がほとんどなかった。そこで高校時代に市民ホールでのアルバイトの経験で培った知識をもとに、必要な備品をリストアップして事務室に直談判するなどして環境を整えていった。
さらに、入学当初の学科の教員は50名の定員に対して4名だけで、照明や音響に関する専門家は一人もおらず、学生たちはそれらを独学で学ばなければならなかった。そんな中、芦辺特任講師は1年目の学園祭でオムニバスの演劇作品10本の照明を担当。新設学科ゆえに十分に整備されているとは言えない環境だったが、それがかえって成長につながったという。
「当時在籍していた教員たちは演技指導の専門家だったこともあり、照明に対しても具体的な指示はなく、演者の視点から感覚的に伝えてきます。それらを再現することにやりがいを感じていました。また、学外で行う公演については、どうしてもわからないことは演劇の名門である宝塚北高校の先生に聞きに行くなどして知識を蓄えていきました」
当時の指導教員は実直で厳しい人だったが、学園祭終了後に芦辺特任講師が担当した照明を激賞。その経験が自信になり、演習で出される作品制作の課題では自ら、照明やサウンドエフェクトを追加するなど制作により一層打ち込み、創作の仕方を学び取っていった。
また、高校時代に目をかけてくれた舞台照明会社から再び仕事を請け負うようになったことも、芦辺特任講師のキャリアに大きな影響をもたらした。大学の最終講義を21時に終えてから現場での“バラシ”作業に参加し、朝の講義に出るというハードな日々を送るうち、仕込みや“バラシ”を効率的に行う技術を習得。大学生でありながら現場チーフに抜擢されるまでに成長し、自ずと照明の道を志すようになっていったという。
5年間で1,200公演もの舞台照明を担当
大学卒業後は、演劇に特化して照明の技術を磨きたいという想いから、東京の舞台照明会社に就職。通常は最短でも3か月かかるとされる研修期間をわずか4日で終え、入社間もなく“即戦力”として現場に配置された。入社1年目の4月から12月までの約270日のうち、少なくとも235日は全国ツアーの仕事で旅に出るなど、多忙な日々を送った。
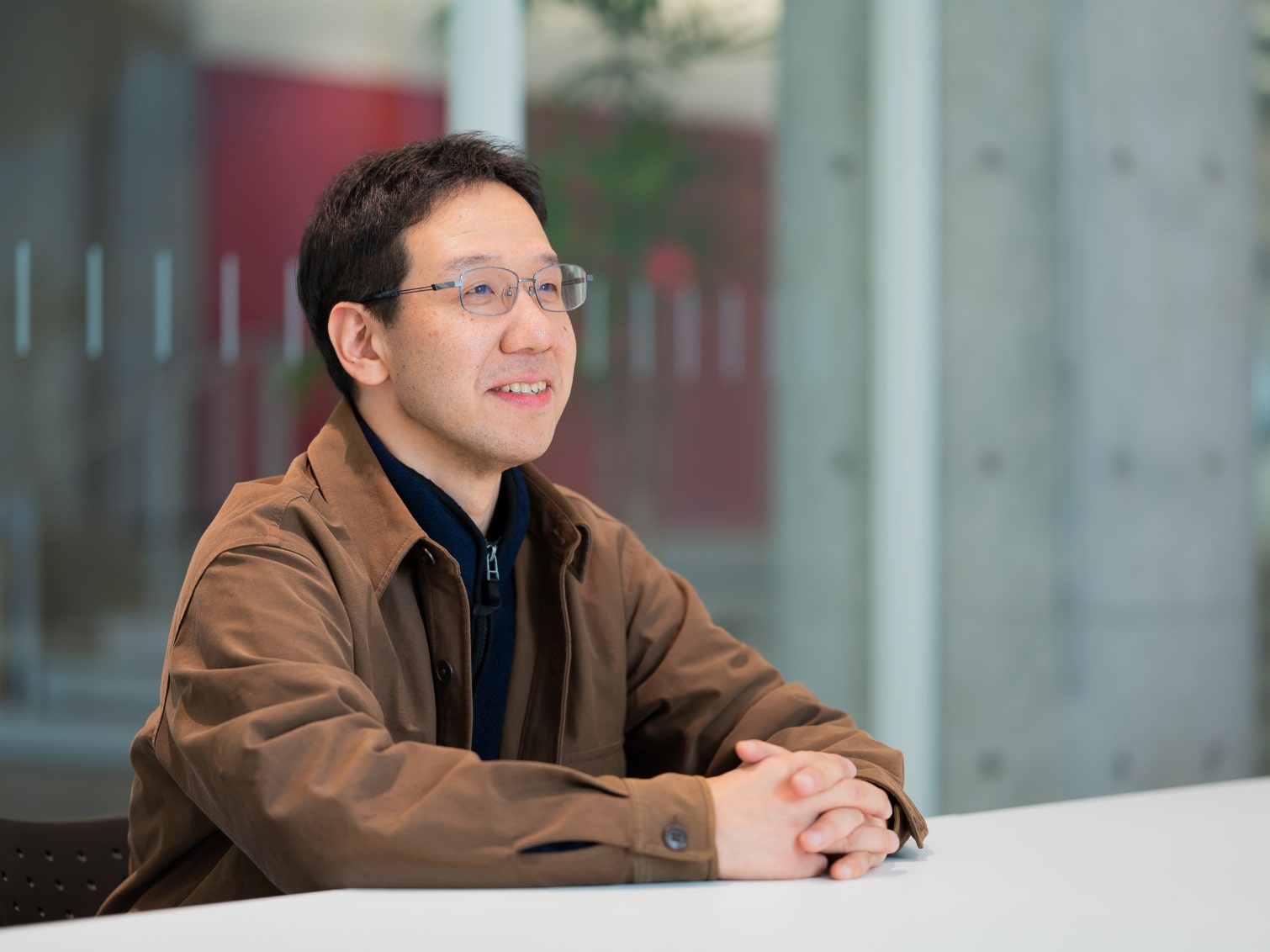
「数多くの現場を経験したことで、臨機応変かつ迅速に対応する能力が身に付きました。現在は仕込み図に指示がすべて書いてありますが、当時は現場入りしてから口頭で簡潔に説明されることがほとんどだったためです。おかげで現在は、13時に会場入りして16時半に開場できるスピード感で仕込みを終えられるようになりました」
在籍した5年間で約1,200公演もの舞台照明を担当した芦辺特任講師はその後、各劇団が独自にデザインした演出のもと公演を行う「プラン」の仕事に時間を割きたい気持ちが高じて、新卒で入社した会社を退職。自身の会社「AITHER」を立ち上げて以降、ストレートプレイやコンテンポラリーダンスを中心とした作品の照明を担当している。
ありとあらゆる選択肢の中から
照明の“最適解”を見出す方法とは?
照明デザインのポイントは
「方向」「強弱」「色」の3つ
冒頭でも述べたように、照明デザインの仕事は奥深い。「光を当てること」と一言で言っても、光を当てる方向や強弱、色といったさまざまな要素を考慮したうえで最適解を導き出さなければならないからだ。これらは照明デザインの基本的な考え方で、中でも最も重要なのは「光を当てる方向」だという。
「1つの対象物に対して、光を当てる方向は25方向あると言われています。正面・背面・真横とそれらの45度ずれで8方向、その対象物よりも高いか低いか同等かという3つの高さを検討すると24方向、最後に真上からの照明を足して25方向です。方向に次いで考えるのは強弱です。2方向から照明を当てる場合は、照明ごとに強弱を変えることもできます。このように考えていくと、1シーンだけでもさまざまな照明の可能性があることがわかります。なお、色は全体の印象を大きく左右しやすいことから、最後に決めるのが基本です」
このように1シーンごとの照明演出を決めた後は、各シーンをいかに“つなぐ”かがポイントになる。
「静止画として成立するような各シーンの照明演出を考えた後は、各シーンを“つないで”いきます。その際にすべてを一気に変化させるのか、照明を1つずつ変化させるのか、早く変化させるのか、ゆっくり変化させるのかといった“つなぎ方”も大切な表現の一つです」
照明家は舞台の“焦点”を司る演出家
しかし、各シーンにおいて方向だけでも25種類ある照明をどのように構成していけばいいのだろうか。“正解が”一つではない照明の世界において、あらゆる選択肢の中から最適解を見出すには、まず各演出のフラットな印象を蓄積して引き出しを増やすことが大切だという。
「講義ではまず照明のありとあらゆるパターンを体験してもらい、自分の中に各演出の印象をストックしてもらいます。学生たちに作品をたくさん観るように伝えているのもそのためです。各照明演出に対して抱く印象は個々人異なる主観で構いませんが、最終的に作品を鑑賞するのは観客ですから、実際に演出する際は主観に寄りすぎていないかを検証しながら、演出を決めることが大切です」
ただし、確実に押さえるべきポイントも当然ながらある。演出を考えるうえでまず重要なのは「見せる/見せない」の判断だという。
「照明を当てた箇所は観客に見せられますし、当てない箇所は隠すことができます。たとえば、サスペンス作品において犯人の顔を序盤で見せたくないときは犯人の顔に照明を当てません。このように『見せる/見せない』の判断を通じて、焦点をどこに置くかを考えることは照明の仕事において最も重要なポイントの一つです」
ジャンル別に見る舞台照明の特徴とは?
芦辺特任講師はセリフや演技によって進行する伝統的な演劇形態であるストレートプレイやコンテンポラリーダンスの舞台照明を専門にしている。舞台照明を要する作品ジャンルにはミュージカルやライブなどがあるが、スモークを焚くなどして華やかな演出を行うミュージカルやライブに対し、ストレートプレイやコンテンポラリーダンスでは各作品に即した繊細かつ緻密な演出が求められる。また、演者の出入りが多いストレートプレイでは演者がつまづいて転倒しないよう配線にも気を配らなければならない。なお、近年はストレートプレイにおいてもスモークを焚くケースが増えてきたことから、以前よりも舞台上のビームライトが目立ちやすくなった点を考慮して演出を考える必要がある。

芸術活動を通じて“生きる力”を養ってほしい
自身の会社を経営しながら大学教員の道へ
自身の舞台照明会社「AITHER」を運営しながら、2019年から桜美林大学 芸術文化学群 演劇・ダンス専修で教職に就いた芦辺特任講師。現在は、舞台芸術や舞台照明に関する授業を担当している。学生たちに対して伝えているのは、「まずは主観でも構わないから自分が納得する絵作りをすべき」ということ。それは作品制作に精力的に取り組む中でセオリーを確立してきた自身の経験に基づいたアドバイスだといえる。また、こうした芸術活動は自分自身の成長のみならず、ときとして他人に影響をもたらすこともあるという。
「舞台照明や演劇に限らずですが、芸術活動は生きることそのものです。自分の創作をする中で自分自身について見つめ直すことなどを通じて、まずは自分が生きていくうえでの力にしてほしいと思っています。その延長線上で、観た人に何らかの影響を与えることもできたらすばらしいですね」
教員紹介
Profile

芦辺 靖特任講師
Yasushi Ashibe
1970年、大阪府生まれ。1993年に近畿大学文芸学部芸術学科 演劇・芸能専攻を卒業後、照明家としてストレートプレイを中心とした舞台照明に携わる。1997年に自身が代表を務める会社AITHERを立ち上げ、現在も舞台照明の仕事に従事。同時に2019年より桜美林大学芸術文化学群 演劇・ダンス専修非常勤講師、2022年より現職。
教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。







