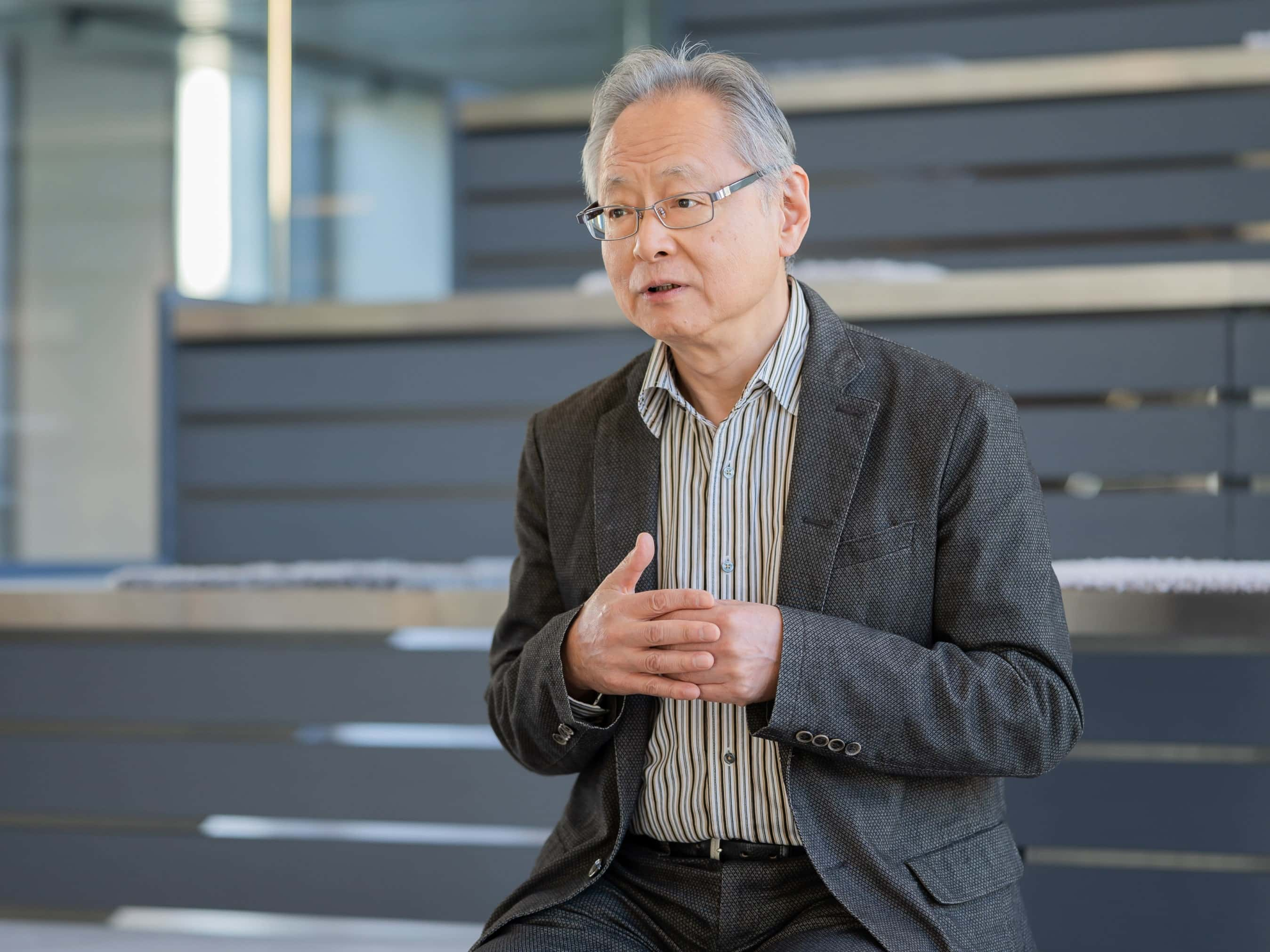メインコンテンツ
市民参加型舞台芸術がつなぐ
新時代の地域コミュニティ
コロナ禍をきっかけにして
舞台芸術の存在が問い直された
新型コロナウイルスの感染拡大は、それまで対面が中心だったコミュニケーションについて再考する大きな契機となった。同時に、演劇をはじめとする対面式の芸術分野にも甚大な影響を与えた。演出家や舞台スタッフ、役者などが集まってチームをつくり、対話を重ねながら作品の完成度を高める。さらに、観客が劇場を訪れ、その場の空気を含めて臨場感や感動を楽しむ。いわばスタッフと演者、観客が対面することによって初めて成立する演劇の世界。プロデュースを専門とし、長年にわたって舞台に関わり続けてきた芸術文化学群の能祖將夫教授にとっても、コロナ期間は演劇という芸術のあり方を問い直すきっかけになった。
「演劇は“群れ”をつくらないと実現しない芸術分野です。生身のつくり手と観客が空間と時間を共有するところに面白さがある。群れをつくって物語を共有するという一体感は、人類が長い歴史の中で繰り返してきた重要な生存戦略のひとつでしょう。私は2000年ごろから、地域の市民が参加する舞台作品のプロデュースと創作に力を入れてきました。しかし、コンサートや演劇やダンス作品は、三密回避のコロナ禍において真っ先に不要不急のものだと見做されてしまった。以前にも増して人と人とのつながりが希薄化してしまったコロナ後の世界で、舞台芸術はどのように地域のコミュニティ形成に貢献できるのか。それが、今の私の大きな関心事です。舞台のライブ感は三密ありきですし、三密は蜜の味ですから、この蜜がコミュニティや人間性の回復に役に立たないはずはありません(笑)」
大学受験を控える中
直感に導かれ演劇の世界へ
能祖教授が演劇に足を踏み入れたのは高校3年生の頃だった。当時を振り返ってみても明確な理由は思い出せない。しかし、大学受験を控える中で、高校生活で何も成し遂げていない自分に対して「このままでいいのだろうか」という漠然とした焦りを感じていたのだという。焦燥感を昇華する先は、小説でも詩でも何でもよかった。だが、その時は迷うことなく演劇だったと言う。
「上の世代に寺山修司、唐十郎、つかこうへいというスーパースターがいたこともあって、時代的にも小劇場演劇が盛り上がっていました。ただ、私にとってはまったく触れたことのない未知の世界。それでも不思議なことに、『そうだ、演劇をやろう!』という直感がありました。そこで、自分と同じようにモヤモヤを抱えた仲間を集めて、生まれて初めて脚本を書いて、地元の市民ホールを借りて上演しました。一行だけ自分のセリフも入れたのですが、舞台に立った瞬間に忘れてしまって(笑)。その瞬間、自分は出る側ではなくつくり手側なんだなと」
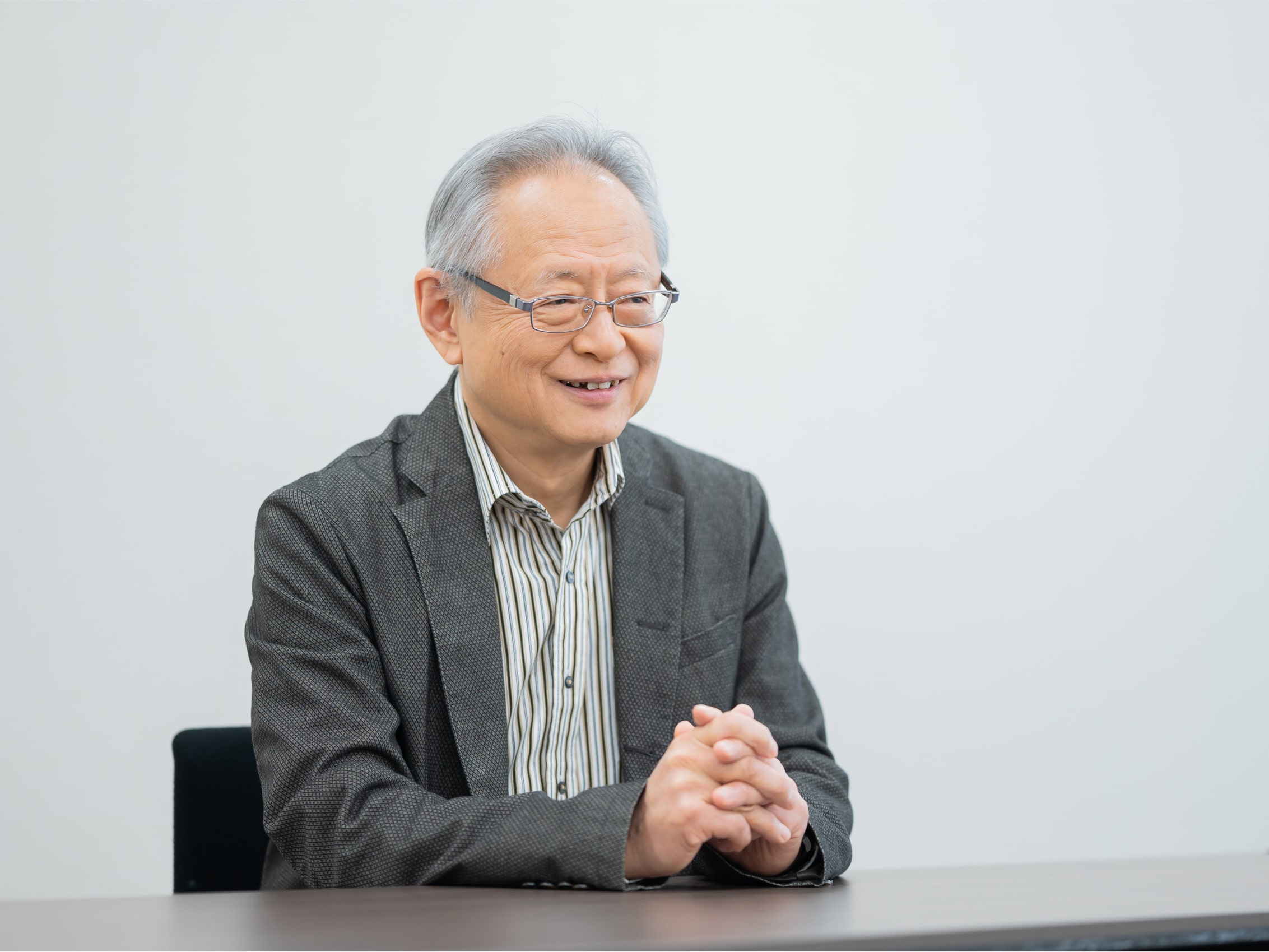
「劇団四季」から始まったキャリア
営業やマネージャーの業務も経験
演劇に関わるうえで
重要な心構えを学ぶ
能祖教授は大学に入ってからも劇団を主宰するなど演劇に携わり続けた。やがて就職の時期が近づくが、自分が社会の役に立つ方法を見出せないままでいた。そんな時、知り合いから浅利慶太氏を紹介される。
浅利氏は「劇団四季」の創立メンバーであり、劇団の運営・管理に当たる「四季株式会社」の代表取締役社長・芸術総監督。演出家としてはもちろんのこと、実業家として日本にミュージカル文化を定着させた人物だ。
当時の演劇界では野田秀樹氏や鴻上尚史氏らが学生主体の劇団を立ち上げ、そのままプロになっていくというムーブメントが起こっていた。しかし、能祖教授は自分の劇団で世に出ていくイメージはなく、浅利氏のいた「劇団四季」に就職することを決めた。
「浅利先生から営業から始めてみるのがいいと勧められました。芝居をつくるためには、お金の流れやスポンサーとの関係を知っておく必要がある。役者であれ演出家であれ、そうした業界の構造を理解しておかなければこれからの演劇界で生き残ることは出来ないよと」
最初に託されたのはミュージカル『CATS』のスポンサー探し。とはいえ、業界どころか社会の右も左もわからない新入社員にとって、そんな大仕事は不可能に近いミッション。当然、新人たちは全員、1円も集めることができなかった。だが『CATS』は無事初日を開ける。実は最初からスポンサーは決まっていて、世間の厳しさを身をもって学ばせるための荒修行だったのだ。一年後、能祖教授は浅利氏に呼び出され、こう言われた。「君がお金の次に学ばなければならないものが何か分かるか?」。首をかしげていると、「人間」だと言われ、「劇団員のマネージャーをやってみなさい」と指示された。
「演劇は演るのも観るのもテーマも人間。人間のことを知らなければ芝居なんてできない、というのが浅利先生の考えでした。役者は、人間の一番綺麗な部分と一番ドロドロした部分を併せ持つ存在。マネージャーとして近くにいれば、人間を知る近道になると言うんです。今となっては無茶苦茶にも思えますが、演出家らしいというか、言葉の力で人を動かすのが上手だと感心しますね(笑)」
2つの劇場に立ち上げから関わり
プロデューサーデビューを果たす
また1年が経ったころ、再び浅利氏からの呼び出しがかかる。東京・渋谷に開館する「こどもの城」の中の二つの劇場、「青山劇場」と「青山円形劇場」に「劇団四季」が関わることになったので、興味があるならそこで仕事をしてみないかという打診だった。能祖教授はそれを受けて財団法人日本児童手当協会(現・財団法人児童育成協会)に入り、立ち上げから両劇場の運営に携わった。
「時代は80年代の小劇場ブーム。それを牽引しているのが私と同世代の才能で、彼らを世の中に紹介したいという思いが強くありました。そこで、企画が通ればプロデュースを任せてもらえないかと上司に提案。ここから、私のプロデューサーとしてのキャリアが始まりました」
時代を切り取った演劇で
話題を集めることに成功
当時の仕事で特に印象に残っているのは、1987年に立ち上げた「青山演劇フェスティバル」。単に劇団を集めて公演するだけではなく、プロデューサーである能祖教授が設定したテーマに沿って新作をつくってもらうことが恒例となった。1997年には、当時は若手だった平田オリザ氏やケラリーノ・サンドロヴィッチ氏、宮沢章夫氏(故人)といった今では日本を代表する演劇人に声をかけ、劇作家・別役実をテーマに氏の戯曲を新しい感覚で解釈して演出してもらった。
「私がプロデューサーとして意識していたのは、週刊誌の編集長のような立ち位置です。電車の中吊り広告を眺めていると、時代を映すような見出しが羅列されていますよね。それを見ているうちに、世の中のトレンドをひとつのテーマで切り取るという点において、編集長とプロデューサーが近い仕事であると気がつきました。例えば、1994年には「女子高生」というテーマを設定。ルーズソックスやコギャルなどの女子高校生文化がムーブメントになった頃で、その年のフェスティバルは大きな話題を呼びました」
市民とプロが共創する演劇に
大きな手応えを感じた
東京を離れて課題に直面し
「市民参加」の可能性を模索
2001年に青山劇場を離れると、茨城県美野里町(現・小美玉市)と北九州市に新しく開館する2つの劇場から声がかかった。人口約2万人の美野里町からは芸術監督、人口約100万人の北九州市から劇場プロデューサーとしてオファーをもらい、その両方に携わることを決めた。このタイミングにおいて、演劇に対する取り組み方の大きな変化があったという。
「人口の少ない美野里町については、住民が参加するプロジェクトをひとつの軸として打ち立てていました。一方、北九州市では東京で実践していたのと同じようにプロの公演を進めようと思っていた。しかし、演劇に関わるプロたち、特にキャストは東京に集まっているんですよね。その現実に改めて直面して、プロ中心の演劇を、東京を遠く離れた地域でつくる意味について考えざるを得なくなったんです」
それでも2〜3年は北九州市にプロを招いて演劇を制作していた。しかし、経済的にもサイクルを回すことに限界を感じるように。そこで、地域の役者やスタッフが中心になって活躍できる企画を作れないかと検討。同時に市民が舞台作品に参加する道も模索し始めた。
「市民参加型の作品へと考え方がシフトしていった際、合唱と演劇が融合した『合唱物語』という新しいスタイルに辿り着きました。市民から合唱希望者を集い、、そこにプロのオペラ歌手やピアニスト、指揮者などを加えたチームで一丸となって物語性のあるステージをつくる。それが話題を呼び、「このやり方でいいんだ」という自信につながりました。プロと市民の一体感、そして生演奏とドラマの臨場感に、観客たちは惹きつけられるのだと思います」

メンバーが異なれば
同じ演劇でも別物になる
こうした手法が成功したことで、芸術がプロだけによって実践されるものだという先入観が消え、プロと一緒に参加する市民にとっても大きな生きがいになるという手応えを感じた。以来、市民参加型作品の創作やプロデュースが能祖教授にとってライフワークになっている。
能祖教授を代表する作品として、プロデューサーと脚本を手がけた『音楽劇 銀河鉄道の夜』がある。大好きだという宮沢賢治の童話を原作に、青山劇場の開館10周年記念として1995年に初演された。能祖教授はこの原作にも市民参加の手法を組み合わせ、学生と市民とプロが共創する『群読音楽劇 銀河鉄道の夜』を新たに創作、2007年から毎年、桜美林大学で行っている。
「何度もやっていてマンネリ化しないのかと聞かれることもあるのですが、これが飽きないんですよね。年によって参加者は入れ替わりますし、それぞれのバックボーンも異なっています。ストーリーは同じであっても、メンバーや時代が変わればまったく違う味わいの作品になるんです。舞台にとって一番大切なのは、誰と一緒に創るかなんです。」
人生の“伴走者”としての芸術が
社会や生活を豊かにしてくれる
プロとアマチュアの境界線や、演劇やダンスや音楽のジャンルを飛び越えながら、舞台芸術を通じて人々が緩やかにつながっていく。地域の連帯感が希薄になりつつある現代において、市民参加型の作品づくりは新しいコミュニティのあり方を提案してくれる。こうした見識を広めるため、芸術文化学群の教授としても学生たちと関わっている能祖教授。次世代の若者も巻き込んだ公演のプロデュースを手がけ、個人の人生を豊かにすると同時に社会全体を潤す芸術の魅力を発信し続けている。
「演劇に限らず芸術というのは、人生の”伴走者”だと思っているんです。いつも生活のすぐそばにあって、日常に彩りや張りを与えてくれたり、傷ついてボロボロになった時には癒してもくれる。学生を含め若い人の中には、芸術を仕事にしたいと考えている人も多くいるでしょう。ただ、それだけが芸術に取り組む意味ではありません。賢治が『農民芸術概論綱要』の中で言っているように、芸術は誰にとっても「明るく生き生きと生活する道」になるはずです。そして芸術の力で結びつくことによって、少しずつでも確実に社会を豊かにしてくれるはず。芸術を通じて世の中に貢献するための方法を、プロデューサー、クリエーター、教員として伝えていくことが私の使命です」
教員紹介
Profile

能祖 將夫教授
Masao Nouso
1958年、愛媛県新居浜市生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。四季株式会社営業部、映画放送部を経て、1985年から16年間、東京・渋谷に開館した「青山劇場」と「青山円形劇場」のプロデューサーを務める。。2001年からは、茨城県美野里町(現・小美玉市)の「四季文化館」芸術監督、「北九州芸術劇場」プロデューサーとして、ともに劇場の立ち上げから関わる。同年4月より桜美林大学文学部総合文化学科非常勤講師、2005年より専任教員、2021年より芸術文化学群・学群長。手がけた主な舞台作品に「月猫えほん音楽会」(青山円形劇場)、「合唱物語 わたしの青い鳥」(北九州芸術劇場)、「神楽オペラ SHINWA」(豊後大野市えいとぴあホール)「群読音楽劇 銀河鉄道の夜」(ストーンズホール/令和2年度児童福祉文化賞受賞)、「マイライフ・マイステージ」(めぐろパーシモンホールほか)、「みつばち共和国」(日本語台本/SPAC-静岡県舞台芸術センター)「合唱物語 沈黙の声」(プロビデンスホール)など。詩人としても活躍し、「第4回びーぐるの新人」受賞。詩集に、『曇りの日』、『あめだま』、『魂踏み』、『かなしみという名の爆弾を』(以上、書肆山田)、『方丈の猫』(七月堂)。2025年4月から桜美林芸術文化ホール館長を兼任。2026年2月に宮沢賢治生誕100年記念「合唱物語 ケンジの祈り」を計画している。
教員情報をみる<at>を@に置き換えてメールをお送りください。