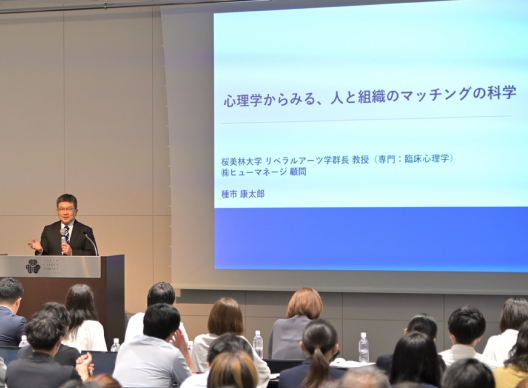メインコンテンツ
50代〜60代がやる気を持って働くには?
産業心理分野からのアプローチ
「エイジングパラドックス」と、働く高齢者のメンタルヘルス
定年延長などで長く働く人々が増えるなか、仕事に対するモチベーションを失ってしまう50代、60代の人が多いと言われている。その一方で、高齢期には身体機能が低下するにもかかわらず、幸福感は低下しにくいという「エイジングパラドックス」という現象があるのも事実だ。世の中における高齢者へのイメージと、個人が実際に抱える心理状態が相反する状況に関心を持ったリベラルアーツ学群の種市康太郎教授が注目したのは、「50代、60代の人たちがいかにやる気を持って働けるか」というテーマだ。
働く人たちのストレスとメンタルヘルスを研究するとともに、産業現場での心理支援を行っている種市教授。職場のストレスが原因で休職・退職する事例が後を絶たないなかで、予防・対策のための研修やコンサルティングにも取り組んでいる。
「ワーク・エンゲイジメント(仕事から活力を得ている状態)が発達的にどう変化していくのかについての研究は、意外にも多くありません。年代別にどのような違いがあるのか、その規定要因が若い方と中高年で異なるのか。そうした事柄を、量的な調査とインタビュー等の質的な調査のどちらからも探っていくことができると考えています」
中高年のワーク・エンゲイジメントを巡る、研究と仮説
中高年のワーク・エンゲイジメントをテーマに研究を行う上で、種市教授は中高年の役職定年者に対象を絞り、役職定年者が抱えている心境の変化やその先のキャリアをどう考えているのかについてインタビューを行う研究方法があるという。そこで重要になってくるのは、若年層との比較だ。
「一般的に若い方の方が仕事に関する権限が少なく、自然とワーク・エンゲイジメントが高まらない傾向があります。権限を持っている中高年のワーク・エンゲイジメントが平均的に高くなるのは納得がいきますが、さらにその先、役職を解かれた後や再就職をした後の60代の方のエンゲイジメントも高い場合があります。その高いエンゲイジメントはどこから来ているのか?ということに注目しています」

若年層と高齢者には、仕事に対して求めるものの違いもある。若年層は自分がどういう人間かを探すための“職業的なアイデンティティ”を求める傾向にあり、新たな環境に飛び込んでネットワークや情報を得ることへの興味関心が強いとされる。一方で、中高年になると既にある関係性を重視する。自分の目の前の環境がどう見えるかについては、発達的な問題もあるのではないか。
もう一つの仮説として、時間展望というものがある。時間の展望が短い人は親密な人とのみ関わって意義のあることだけに集中するので、幸せに感じるという研究があるという。一方で、時間展望が長い人の方が仕事への満足度が高いという研究もある。一致していないようにも見えるが、自分に残された時間がどのくらいあるか、どれくらい自分が活躍できると考えられるかという、未来に対しての認識もワーク・エンゲイジメントに影響を与える可能性はあるだろう。
「20代〜30代の方と40代、50代以上の方には違いがあると思うので、あまり一般的なキャリア理論でくくらない方がいいと思っています。自分も中高年に入ってきているということもあり、『人生の後半をどう考えるか』という視点で研究をしたいと思っています。そういった知見を踏まえて、企業におけるキャリア研修などにもつなげていきたいですね。実際に、現在もそうした研修を開発し、企業において行っています。社員同士のグループワークをするなかで見えてくることも多いので、面白いですね」
実践的研究からはじまった「職場のメンタルヘルス」への関心
大学時代の恩師がきっかけに。企業研修との出会い
種市教授が専門を「職場のメンタルヘルス」に定めたのは、大学時代に所属した研究室の影響があった。学部・大学院時代に師事した恩師が自動車メーカーの研究所と建設会社の2カ所でカウンセリング業務を担当しており、弟子入りする形で研究活動を始めた。
大学時代の種市教授もまた、学生ながら企業での実践的な活動に従事したという。大学院入学直後から大学の助手の勤務を終えるまでの約8年間、社員へのヒアリング、カウンセリング、ストレス調査などの活動に取り組んだ。
「研究をどう社会実装するかということが大事だと言われていますが、私はむしろ現実の要請から研究をはじめているところがあります。そういう意味では科学的研究のスタイルと違う部分もありますが、目の前にある現実に対してどう考えるかという取り組みはとても面白いです」
「職場のメンタルヘルス」の研究領域は、企業勤務を経て、教員に転身した研究者が手がけるケースが多いが、種市教授は、一貫してアカデミアの立場で研究に取り組んできた。そのため特定の業界や職種に縛られず、時代のニーズに合わせて、就活生から中高年世代まで、幅広いターゲットの研究データを収集してきた。
産業心理の分野を追究する過程で、公認心理師、臨床心理士、精神保健福祉士、キャリアコンサルタントなどの資格も取得しており、現在も企業向けにメンタルヘルスの研修やコンサリティングを行っている。近年は日本産業ストレス学会常任理事など数々の業界を統括する役職に就き、人材系企業の顧問も務めている。内田クレペリン検査など臨床心理検査にも造詣が深く、豊富な経験と知見は、幅広い業界から注目されている。

中高年の培ったものを棚卸しする、企業研修の取り組み
40代、50代の方向けに行う具体的な研修として、種市教授は「人生の展望」に焦点を当てる。研修当日を迎えるまでの下準備として、参加者には入社してからこれまでに至る数十年間のキャリアをライフラインという形で描き、経歴と展望を書き出してもらう。さらにその時、どんな人から影響を受けてきたかを共有してもらうことも重要だという。
「新しいことを伝えるというよりは、それぞれの方が今までのキャリアを振り返って、どう考えるかを話してもらうような研修です。前述の発達的な理論をお話した上で、個人のことを社員同士で共有してもらう。その議論を踏まえて、これから先の展望を考えてもらうのです」
培ってきたスキルや知識など、いわゆる「キャリアの棚卸し」を行うことと同時に、他にその人が持つ資産を可視化することも重要だ。身体的な健康や活力、社会的な健康という側面では、家族や友人との関係性も個人の持つ資産だと言える。
「社会的孤立が世の中の課題になるなかで、人間関係も大きな資産だといえます。それがないと、自分が培ってきたものを意識できなくなる可能性もある。当然ながら、みなさんは何も持っていないわけではない。スキルや知識を整理した上で、心構えを含めてその人自身が備え持っているものをどう活かしていくのかを、研修では考えていきます」
時代により変化する、産業心理への探究
近年の研究、テレワーク下における上司と部下の関係性について
2008年から桜美林大学に勤務し、リベラルアーツ学群を担当する種市教授。2011年の東日本大震災をきっかけに、災害時の心理的応急処置「サイコロジカルファーストエイド」のトレーナーとしての活動や研修効果の研究を行うほか、学生時代から専門領域として持っていた「産業心理」の取り組みを続けている。近年では、コロナ禍の影響もあり、テレワークの環境下における精神的な健康についての研究を行っている。
「テレワークだと特に、上司と部下のコミュニケーションが精神的に強く影響を与えます。上司のコミュニケーションが上手だと部下のエンゲイジメントが高くなり、その逆もあるとわかっています。その違いが、対面で仕事をする場合よりもテレワークの場合の方が大きく、明確になるようなんです。対面だと知らず知らずに周囲が補っていた部分が、テレワークでは補われないといったことも要因としてあるのかもしれません」
コロナ禍でテレワークの就業環境が一般的なものになった一方で、対面での仕事に戻そうとする動きも強くある。産業心理は時代による変化が激しく、研究テーマも常に変化する。
「産業心理に関心があるというよりも、人間が何を考えるのか、どう思っているのか、ということに興味があるのかもしれません。マクロな傾向よりも、さまざまな社会問題に対して一人ひとりがどのような思いを抱くのかに、心理学的な研究ができると面白いと思います。10年後の50代と、現代の50代ではきっと考えることも違って一般化できない。今の時代の人々が、その先の人生をどう考えているかにますます興味があります」
教員紹介
Profile

種市 康太郎教授
Taneichi Kotaro
1994年 早稲田大学 第一文学部 哲学科心理学専修 卒業。2001年 同大学大学院 文学研究科 心理学専攻 博士課程単位取得満期退学。2001年 早稲田大学大学院 にて博士号取得。聖徳大学 人文学部心理学科にて講師、助教授、准教授を経験後、リベラルアーツ学群の准教授として桜美林大学に在籍。2016年に教授。2018年から2024年まで領域長(人文)、2024年より学群長。近年は、日本産業ストレス学会 常任理事、日本産業精神保健学会 理事、日本公認心理師協会 常務理事、日本心理臨床学会 理事、株式会社ヒューマネージ顧問など多くの役職を任されている。
教員情報をみる